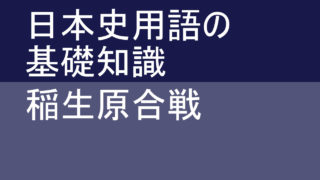 あ~お
あ~お 稲生原合戦【織田信長 対 織田勘十郎(織田信勝)】
稲生原合戦について【表記】稲生原合戦(稲生合戦)【読み】いのうはらかっせん(いのうかっせん)【時代】戦国時代稲生原合戦とは弘治2(1556)年に、織田信長と織田勘十郎(織田信勝)との間で行われた合戦。(『織田信長像(部分)』長興寺所蔵 Wi...
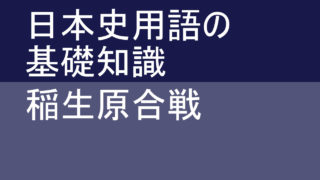 あ~お
あ~お 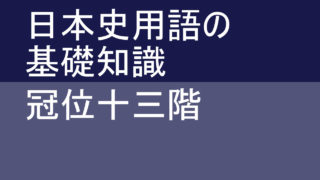 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 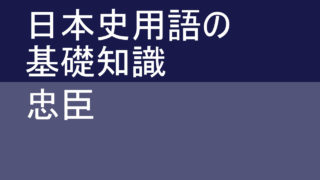 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 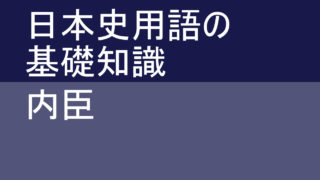 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 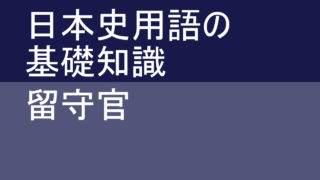 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 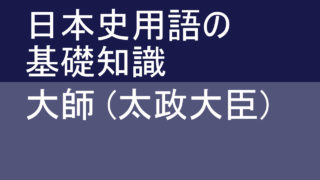 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 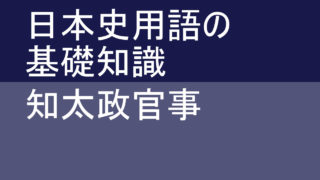 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 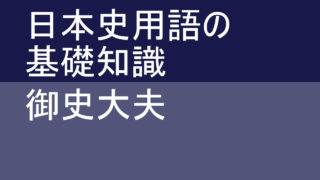 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 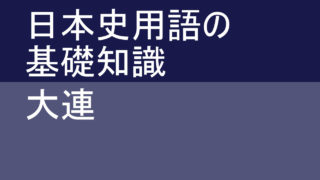 あ~お
あ~お 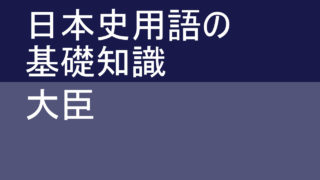 あ~お
あ~お