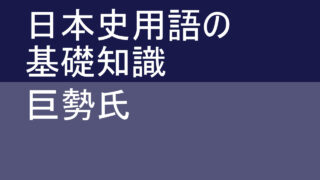 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 巨勢氏【大臣として継体天皇を支えた豪族!その後、日本美術界のビッグネームに!】
巨勢氏について【表記】巨勢氏・許勢氏・己西氏・既洒氏(『百済本紀』)【読み】こせし(こせうじ)巨勢氏とは【始祖】武内宿禰(建内宿禰)【属性】在地系皇別豪族【姓】臣・朝臣(『八色の姓』)オオヤマトネコヒコクニクル大王(孝元天皇)の流れである武...
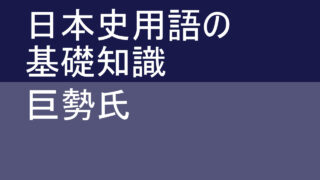 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 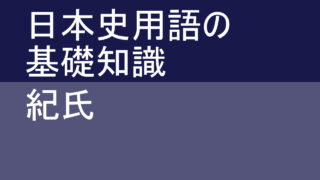 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 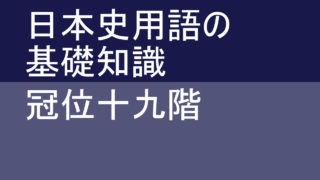 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 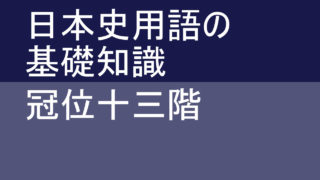 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 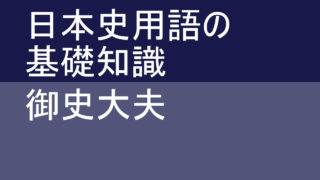 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 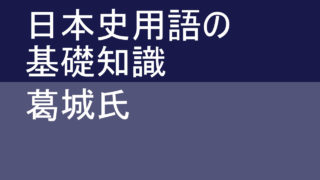 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 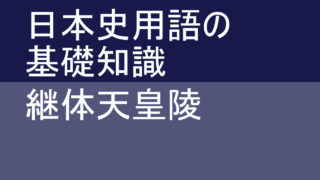 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 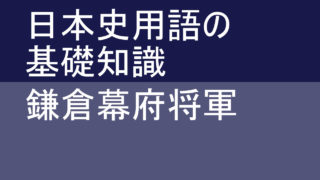 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識  日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 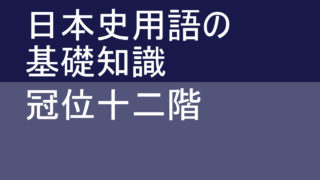 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識