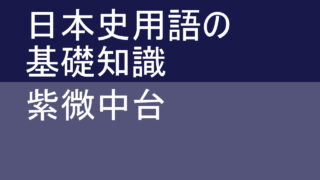 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 紫微中台【奈良時代に登場したもうひとつの「太政官」!】
紫微中台について【表記】紫微中台【読み】しびちゅうだい【時代】奈良時代紫微中台とは藤原光明子(藤原不比等の娘)の立后に際し設置された令外官「皇后宮職」を母体として、唐風に呼び改めた令外官。光明子は、娘である孝謙天皇が即位したことで、皇后(光...
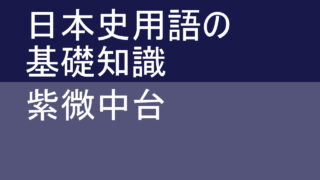 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 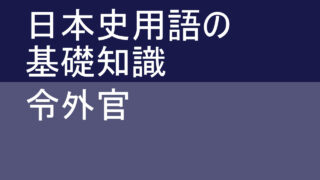 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 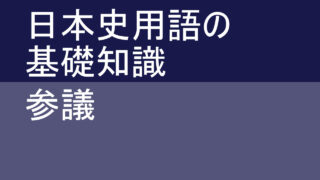 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 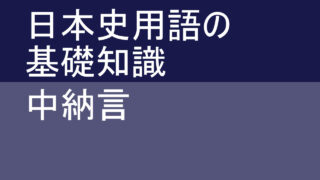 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 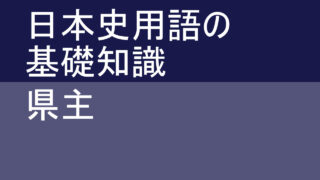 あ~お
あ~お  あ~お
あ~お 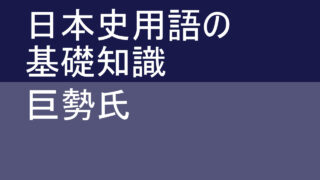 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 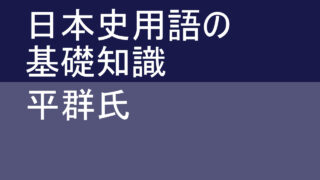 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 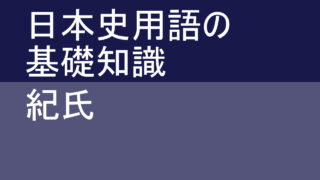 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識 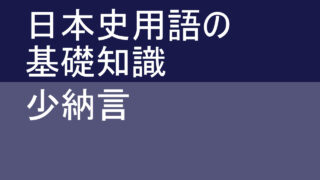 日本史用語の基礎知識
日本史用語の基礎知識