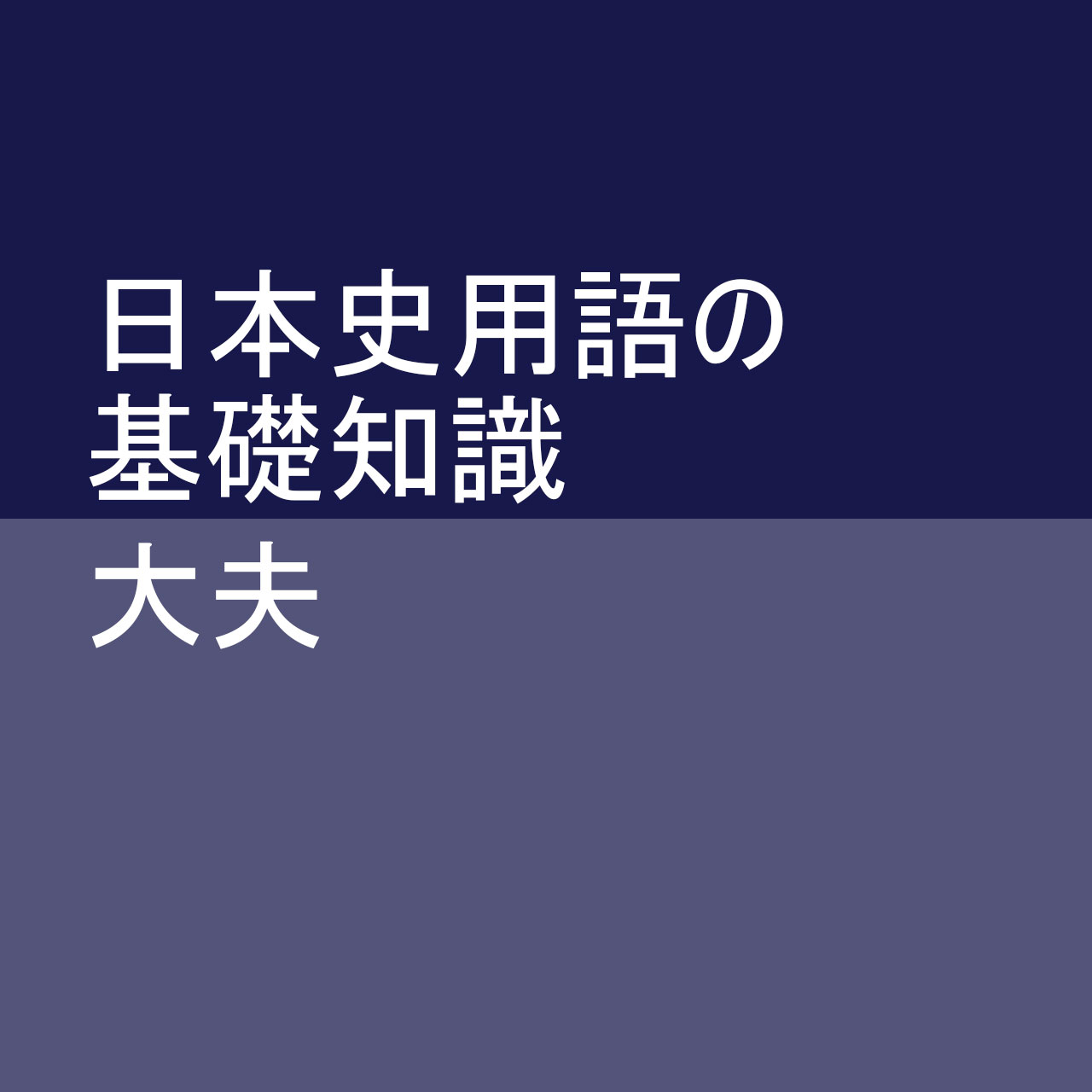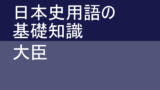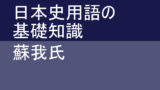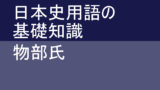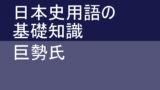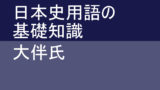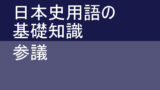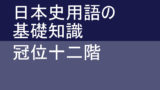大夫について
| 【表記】 | 大夫 |
|---|---|
| 【読み】 | まえつきみ(たいふ) |
| 【別表記】 | 群卿・群臣 |
大夫とは
古代。
上級官人のこと。
大臣に次ぐ官職で政策の協議運営に関与した(後の律令官制の四位以上相当と見られる)。大夫には、主として有力豪族から選出され構成された。
《イメージ》 天皇 ┃ 大臣 大連 ┃ 大夫 大夫 大夫 ┃ 豪族 豪族 豪族
大夫と成ることが可能であった有力豪族は、蘇我氏・物部氏・阿倍氏・巨勢氏・大伴氏等に限られた。
古代の「大夫」職は、律令体制への移行が進むに伴って、「上級官人」職へと変貌を遂げていくこととなる。
後の令外官である「参議」は大夫が発展して置かれた日本独自の官人制度とする見方がある。
大夫の変遷
推古天皇12(604)年正月、『冠位十二階』に従って冠位制度が施行される。
同年4月、『憲法十七条』が公布される。
『群卿、百寮、禮を以て本とせよ。其れ民を治むるが本、要ず禮に在り』
(『日本書紀 下 日本古典文學大系68』坂本太郎 家永三郎 井上光貞 大野晋 校注 岩波書店)
この時点で大夫たちの政治への参画が方針として示される。
大化元(645)年6月、蘇我氏本宗家が滅ぶ。
大化2(646)年正月、所謂『改新の詔』が出される。
この詔の第一に大夫の食封(俸禄・給与)の加増が発せられる。
『大夫は、民を治めしむる所なり。能く其の治を盡すときは、民頼る。故、其の禄を重くせむことは、民の爲にする所以なり』
(『日本書紀 下 日本古典文學大系68』坂本太郎 家永三郎 井上光貞 大野晋 校注 岩波書店)
これは改新政権運営の実務の中心が大夫たちであるということに他ならない。
同年8月、新官制公布が公布される。
『舊の職を改去てて、新たに百官を設け、位階を著して、官位を以て叙けたまはむ
(『日本書紀 下 日本古典文學大系68』坂本太郎 家永三郎 井上光貞 大野晋 校注 岩波書店)
ここに、新しく百官・新冠位が制定されることとなる。
こうして、「大夫」は形式上の姿を消す。
大夫の年表
年表
- 推古天皇12(604)年正月1日冠位が諸臣(まえつきみ)に下賜される。
- 4月3日「憲法十七条」公布。
- 推古天皇36(628)年3月7日推古天皇、崩御。
- 大化元(645)年6月12日『大化改新(乙巳の変)』。
- 大化2(646)年正月1日「改新の詔」。
- 8月14日新官制公布。