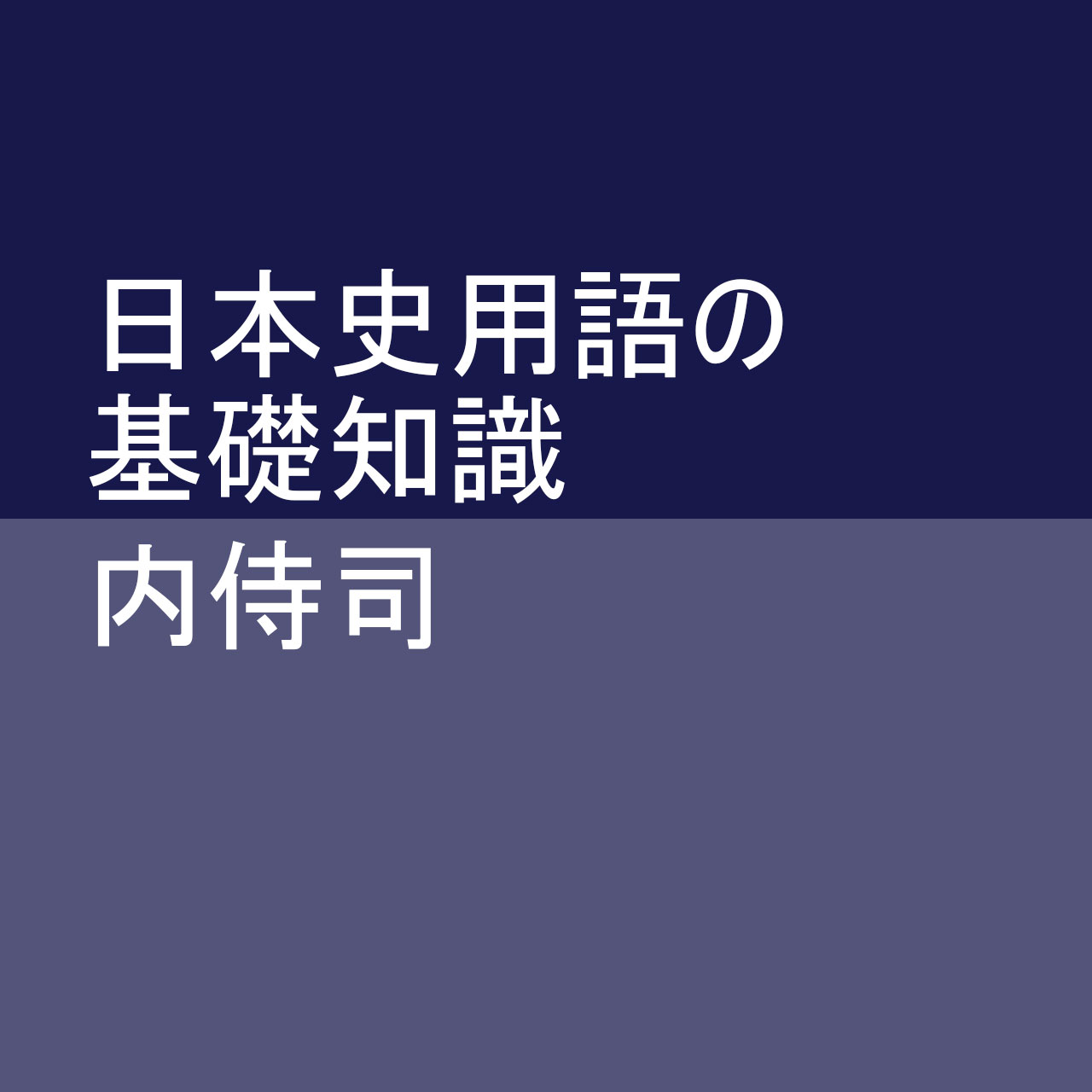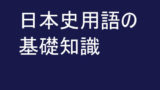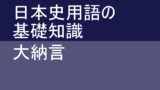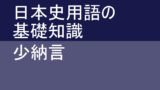内侍司について
| 【表記】 | 内侍司 |
|---|---|
| 【読み】 | ないしのつかさ(ないしし) |
内侍司とは
律令体制下の官職で、後宮十二司のひとつ。
「後宮職員令(『養老律令』)」によって規定された官司。
中務省の管轄下に置かれていた。後宮で、天皇の側にあって、奏請・宣伝・禁内の礼式への供奉を司る職。
職務権限としては、後宮の大納言・少納言とも言うべきものであった。
ただし、当初の季禄は、如何なる理由からか、蔵司・膳司・縫司よりも下に位置づけられた。
内侍司の変遷
平城天皇の寵愛を受けた藤原薬子が、尚侍に任命され、その格式も一挙に従三位相当にまで引き上げられたことから、尚侍は、天皇の側室としての意味合いも持つようになる。
こうして、権限の強くなった内侍司からは「内侍宣」が出されるようになる。
このような内侍司の変遷を前に、有力な貴族層は、後宮支配の職として一族の女子を配するようになって行く。
やがて関白であった藤原兼家の娘の藤原綏子が、尚侍から居貞親王(後の三条天皇)の「東宮妃(皇太子妃)」となり、俸禄も女御と同格の扱いを受けるようになると、以後、この綏子を先例として、尚侍は、東宮妃へ進むための形式上の官職となってしまう。
この結果、尚侍は官人としての意味を失う。
また、典侍も天皇の側室としての意味合いを持つようになり、実質的に令制で規範された妃・夫人・嬪等と同様に扱われたために、遂には掌侍が内侍司を統括するようになる。
従って平安時代の中期以降、「内侍」とは、掌侍のことを指す。
掌侍の筆頭者は、「勾当の内侍」、「長橋殿」と呼ばれ、掌侍の下に権掌侍が設置された。
内侍司における役職と職務内容
《役職》 尚侍(准従五位、後に准従三位)2名。 常時、奏請宣伝。 女嬬の検校。 内外命婦の朝参の管理。 禁内の礼式に供奉。 典侍(准従六位、後に凅従四位)4名。 尚侍に同じ。 ただし奏請宣伝を行えない。 尚侍に欠員がある場合のみ奏請宣伝を代行出来る。 掌侍(准従七位、後に准従五位)4名。 尚侍に同じ。 ただし奏請宣伝を行えない。 女嬬100名。 一般業務
命婦とは・・・
内命婦は、五位以上の官位を与えられている女性のこと。
外命婦は、五位以上の官人の配偶者のこと。
形式的となった内侍司における「尚侍」職
藤原道長の三女である藤原威子の例
『大とのゝ内侍の督の殿内へ参らせ給。よろづ調へさせ給へり』
(『榮花物語 上 日本古典文學大系75』松村博司 山中裕 校注 岩波書店)
寛仁2(1018)年、威子は、後一条天皇の後宮に入った。
内侍司の年表
- 天平宝字4(760)年12月12日淳仁天皇、尚侍の封戸・位田・資人を男性官人と同じだけ支給する。
- 宝亀8(777)年9月17日光仁天皇、尚侍を蔵司の尚蔵と、典侍を蔵司の典蔵と、それぞれ官位と俸禄を同じとする。
- 宝亀10(779)年12月23日光仁天皇、内侍司の女官らの俸禄を、蔵司に準じたものとする。
- 大同2(807)年12月18日平城天皇、内侍司に勤務する女官の官位を引き上げる。
- 大同4(809)年正月藤原薬子、従三位叙位。